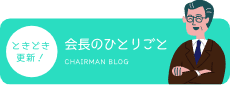写真週刊誌ってものは・・・
2024-03-29
人間ってスキャンダルが好きですね。
人の不幸は蜜の味ってやつですか。。。
そりゃあね、私も聖人君子ではないので結構好きというか、興味のあることなら深く知りたいという欲求はあります。
けど、それが度を越したらやはり良くないのではと思うわけで。
写真週刊誌が某有名お笑い芸人のスキャンダルを報じ、裁判にまで発展してますが裁判の争点がいまいちよくわからない。
週刊誌は事実確認が取れない事象を一方的な論調で断罪していてこれまで積み重ねてきたキャリアやイメージ(元々芸人はそんなもんだと思うが・・)を損害し活動に支障が出た。
まぁ、一方的という意味ではその通りだなと感じる。
訴えた女性は匿名でそういう事象は「あったんだ!」と訴え。
訴えられた芸人は実名で、何なら今回と関係ないことまで非難されている。
もちろん事実はわかりません。女性の言う通りかもしれないし、嘘かもしれない。
もし嘘だったら大問題です。どんな人でもどんな内容でもでっち上げられるわけですから。
本当ならばしっかり謝罪するべきです。相手が何を望むかわからないけど。
昔ならしょうがないやつだと冷たい視線投げるぐらいで済んだかもしれないけど、今は罪はもちろんだけど強烈なレッテルを貼り付け社会復帰すら許さない私刑が執行されるのが現状です。
また、週刊誌側がまるで正義みたいな、自分たちがゲームチェンジャーであるように振舞っているのは危険ではないだろうか。
ペンは剣より強しとよく言ったものだが、あまりにも強い力を持っていると過信や強権を振るってしまうのは違うような気がする。
マスコミは警察機関ではないので家宅捜索や逮捕権、ましてや人を裁く権利もない。
事件であればしっかり警察や司法に委ねるべきであって、社会を動かす切っ掛けを作るのがマスコミの仕事ではないか。
あまりやりすぎるというか、徹底的に個人を焼け野原にしてしまうのは個人的には後味が悪い。
そこに何が残るのだろうか。
人は家族と楽しく笑って過ごすのが何より幸せなのではないだろうか。
双方笑顔になれる道を見つけることはできないだろうか。
想像力とは
2024-02-18
想像力が乏しい人っていませんか。
「こんなことしたら大変なことになる。」
「こんなこと言ったら相手を傷つける。」
端から見たら簡単にわかりそうなものなのに本人には見えてないのか、そもそも考えていないのか。
他にもこんな時ありませんか。
「ここまで来たのだからあれを買ってこよう・食べよう。」
「これをしておいたら○○さん喜ぶんじゃないかな。」
「ここまでやったんだからついでにこれもやっておこう。」
プライベートでも仕事でもこんな場面沢山あると思うのだけど見えていない人は思わないし、やらない。というか言われたこと以外の事をやるのが恐いのかな。
失敗は誰しもしたくないけど、それがチャレンジした結果であれば例え失敗しても責められることはないのではないだろうか。
むしろ、チャレンジしないことが咎められるような感じがするのは私が昭和な人間だからか。
想像力を膨らませて、見えない相手が何を望んでいるのか、何を知りたいのか、きっとこれを質問してくるとか、こんな行動を起こすとか先回りして考えておけばきっと焦らないし、それが準備ってものでしょ。
準備した上でそれを超えた事態が起きるのが想定外というもののはず。
そんな物足りなさを感じてしまうのが今の時代は異常なのかな。
好きなことならやり過ぎてしまうぐらいの情熱を持ってもいいのではないか。
余計なことかもしれないし、お節介なのかもしれないがこれからも世話焼きのアナログ人間でいたいなと心のどこかで思っている。
なんだか河島英五の「時代おくれ」の歌詞みたいになってきたかな。
たまにスナックなんかで歌う人いるけど、本当に時代的には違うけど心に沁みる歌ですよね。
あの曲を歌えるほど人間出来てないし若輩だけど、男が惚れる男の姿があの曲の男だよね。
何を言いたいのか相変わらずわからなくなり論点がズレてきましたが。
とにかく想像力・思考をめぐらす・行動するが大切だな。
難しいことじゃない。考えることなんて。
人間一人では生きていけないのだから、目の前やその先の相手の気持ちを想像してみよう。
御役所仕事・・・
2024-01-16
やっぱりね
住宅セーフティネット制度って知ってますか?
郡山市は、空き家・空き室をお持ちの賃貸人(大家・不動産店等)と住宅確保要配慮者(さまざまな理由により入居を拒まれやすい属性の人)の中でも特に収入が低いひとり親世帯とのマッチングを行うために、令和4年度に新たな住宅セーフティネット制度を活用した家賃と家賃債務保証料の補助事業を開始しました。
(出典:郡山市役所ホームページ)
というような制度で、なかなか賃貸住宅を借りづらい人などのために賃料の一部を補助しましょう(上限あり)ということなんですが、これ表面的に見れば大家さんも入居者も助かってwinwinな感じなんですが、どうも広がっていかないんですね。
なぜでしょうか?
答えは、手続きが面倒だから!
今回、弊社でも入居者様のご希望があって初めて大家様に制度のご説明をしてご理解いただき、物件登録・契約へと手続きを進めていますがなかなか先に進まない・・・
弊社の担当者が市役所の担当者と電話しながらアレコレやってるわけですが、なぜ行政は手続きを複雑にしたがるのでしょうね?
生活保護の方などの時もそうなのですが、役所で借り上げするか、通常の賃貸借契約を交わし賃料相当額を補助するとかもっと効率的な方法はあるはずです。
それなのに、アレが欲しい、コレが必要、この書類を追加で提出して・・・と。
これいつも言いますが、やる気あるんですか?(これは窓口担当者ではなく、制度を決めている方に言ってます)
本当に困っている人にはちゃんとした救いの手が必要なんですよ。
なんとなく制度作って、やってます!感を出さないでください。
震災の時も感じましたが、今現在の能登の方々もそうです。
今この瞬間に落ち着ける場所が必要なんですよ。
民間でできることは最大限協力しますが、それだけでは解決しないのが現実で、それを補うのが国であり、都道府県であり、市町村なのではないでしょうか。
何でも国でやれ!なんて言わないですよ。
自助は当たり前ですが、人を支えるのも国の仕事として当たり前ではないでしょうか。
官僚なんて本当に頭のいい人が集まっているんですから頭のいい制度・方法・手続きを考えてください。
政治家は当てにならないのだから。
私としてはもっとシンプルに考えていいんじゃないかと思いますけどね。
ジャニーズ事務所問題を考える
2023-09-12
故ジャニー喜多川による史上類を見ない性加害事件に端を発し大きな関心が社会に蔓延している。
そもそも、ジャニーの問題など郡山の片田舎に育った私のような者でも昔から聞いたことがあるし、一種の業界のタブーだと思っていたので今更感が拭えないのが本音である。
しかし、被害者からしてみれば一生残る心の傷であり、恨みは消えないのは当然だと思う。
さて、この事件(事変という人もいる)に対して、今後の注目点は、
①被害者に対する補償
これはおそらく長期化するだろう。被害者の会なる団体が発足していてその団体が窓口となって交渉していくのだろうが焦点は示談金。結局は金額次第なのかな?という流れになってませんかね。
理想的なステップとしては、被害者認定を行い、被害者を可能な限り一堂に集め、ジャニーズ事務所の株主・取締役などが額を床にこすりつけ土下座(無意味のようだが被害者感情を考えて)し、次に示談金を一律に決定する。
これを迅速に、メディアを入れて一般公開型で行えば良いと思う。
金額は過去の性犯罪の示談金を目安にするのが公正ではないだろうか。
しかし、被害者の会は何やらきな臭い動きをしているようだ。
やれ基金を作れ。事務所の売り上げの3%を差し入れろ。国が関与しろ。
申し訳ないが、世の中にいる性犯罪の被害者の方はみな等しくおぞましい事件により傷ついていて比べようがないが皆そのような基金を立ち上げ、犯人の給与を差し押さえ、国に補償しろと動いているだろうか。
被害者すべての生涯の生活を支えるのは少し求め過ぎではないかと思う。ましてやそこに税金を投入するのはハッキリと反対する。我々国民は加害者ではない。
納得いかないならば、日本は法治国家である。正々堂々と司法に訴え、粛々と決めた方が後腐れ無いと思う。活動家は寄生するな。
②社名の継続か変更か
社名変更は必要でしょう。ただし、じゃあどんな名前ならいいの?かっこいい名前だと反省していないだとか何考えてるとか言われそうだし、結局名前変えても報道されるときは○○(旧ジャニーズ事務所)と言われるのだろう。
難しいので、いっそ事務所は解体するのがいいのではないだろうか。
被害者救済財産管理会社として会社を残して、各々の活動は移籍した方が両方にいいだろう。
③所属タレントの今後(スポンサー・メディアの対応)
ここは②でも述べたように各自移籍するか独立するなどして出直した方がいいのではないだろうか。
幸い名が売れている方も本当に実力がある俳優や歌手もいるので旧事務所に恩義や愛着はあるかもしれないが早く動く方がいいと思う。
マスコミやスポンサーは知っていたはずなのにむしろ被害者みたいな顔して番組やCMを降板させ、番組に出演をさせないように干そうとしている。
世間に支持されていて実力のある人ならば継続してても文句は出ないのではないか?世間の風潮に忖度してるだけならばちょっとダサい。
我が福島県でもお世話になっているTOKIOは本当に福島を愛してくれて県民は感謝している。できるならば完全独立して引き続き福島県のために活動して欲しいし応援し続けたい。
先日の記者会見はもはやコントかと思うほどの内容であったが、第三者委員会からの提言を受けてからの準備では限りがあるし、持ち株100%の企業で対応を代表者以外が決めていけるはずもないので仕方ない。あの場はジュリー前社長の責任である。
被害者の方に対しては私が言っていいのかわからないが本当に同情しますし恨めしいと思います。一刻も早く本件が解決に向かうことを祈念いたします。
ただ一点、本当に解決・和解に向けて納得のいくまで対話を諦めないで欲しい。他人や変な活動家に惑わされずに自身の声で、気持ちで相手と対話して欲しいなと思います。
防犯意識を持ちましょう。
2023-07-13
冷や汗タラタラ
ご無沙汰しています。
ブログのネタがなくて更新できていませんでした。
今回はどうしても言っておきたいことがありまして書きました。
何かと言えば、実は以前も書いたことなんですが
防犯意識を持って欲しい!!
先日、アパートの退去に際しまして玄関ドアの電子キーの暗証番号を入居者様より聞いたところ、初期設定の番号と同じでした。
理由を聞くと、変えようと考えていたが面倒くさくなり、結果そのままで使っていたとのこと。
まぁ、よくあることなのですが怖いのはここからの話です。
このアパートは昨年より4部屋の入れ替わりがありました。
つまり4件の退去もあったわけですが・・・
実は、この4件の方全てが同じ初期設定の暗証番号のままお住まいだったのです。
私の言いたいこと、わかりますか。
怖いです。
事件がなくて良かったです。
お願いなので、面倒くさくても暗証番号は必ず変えてください!!
何かあってからでは遅いのでお願いします。
現場からは以上です。